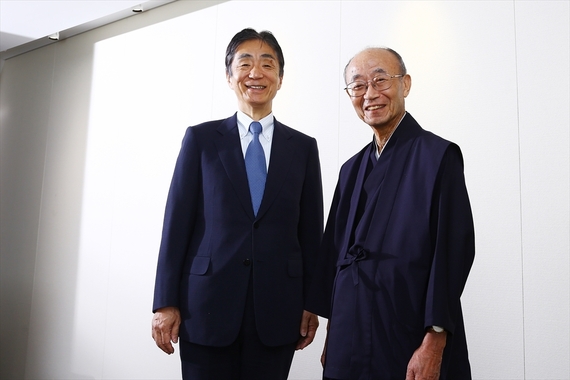山折座長と対談していただく4人目の有識者には、慶應義塾大学前学長で、現日本学術振興会理事長である安西祐一郎氏を迎えて、4回に分けて日本の教養と知識人について語ります。
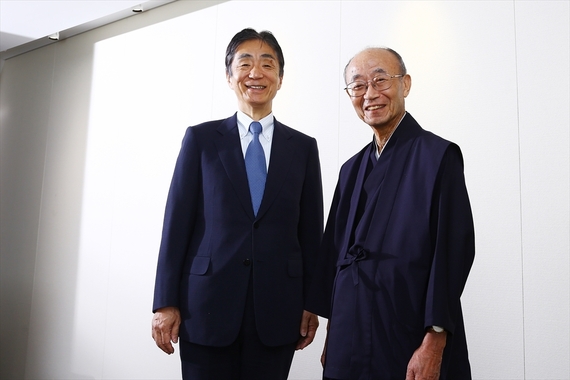
――今回の対談では、「教養」と「大学」、そして中学高校など、教育全般ついて伺いたいと思います。安西さんは「日本の大学は終末期を迎えている」と指摘していますが、まずその理由をお話しいただけますか。
安西:「終末期を迎えた日本の大学」ということの意味は、戦後の長い間に堆積されてきた日本の大学の機能が、時代の移り変わりとともに末期を迎えているということです。
総論として、これまでの時代は、大学生が受け身の教育を受けて自動的に社会に出れば、そのまま社会の階段の中で暮らしていくことが可能でした。大学は一斉授業を行い、学生は授業に出さえすれば単位が取れて、卒業時期には就職活動をやればなんとなく就職ができる。そして企業に行けば企業の中で、普通にやっていれば暮らしていける――そういう時代が長く続きました。そうしたシステムの土台として、大学は機能してきましたが、そうした時代が終わりにきているのではないかという問題提起です。
なぜ小林秀雄がセンター試験に出たのか
山折:最近、私は「大学にささやかな異変が起こっているのかな」と、プラスの意味で思ったことがあります。それは、2013年のセンター試験の国語の科目に、小林秀雄の文章が出題されたことです。刀の『鐔(つば)』という、昔、私も学生時代に読んで非常に感銘を受けた文章が出ました。ところが、多くの学生はそれを理解することができなかったために、平均点が前年より16.91点も落ちてしまったのです。それに対して世間では、「なぜあんな難解な文章を出したのか」という批判が多く出ていました。
私はこの問題に関して、大学入試にかかわった大学の助教授クラスの人間に意見を聞いてみたのです。すると、彼らが異口同音に、「ここ20~30年、小林秀雄の文章は非常に人気がなかった。理系の教師はもちろん、社会科学系の教師たちの間で特に人気がなかった」と言っていました。
それはなぜかというと、まず論理的ではない。わかりやすくない。つまりコミュニケーションのための言葉としては不十分だから、入試問題に出すべきではないという意見が強かったそうです。ただし、僕ら文学の世界で育ってきた人間からすると、小林秀雄は文学の神様と言われてきた人であり、多くの影響を受けた人間が僕の知り合いにもたくさんいるわけです。
では、なぜその小林秀雄の『鐔』が出題されたかを考えると、もしかすると3.11の影響かもしれないと思ったのです。つまり、人間とは何か、人間いかに生きるべきか、を問うたのが小林秀雄の文章そのものだということです。
その対極にあるのが、たとえば丸山眞男の文章です。論理的で、説得力があってわかりやすい。そういう対称性の中で、戦後の大学教育は丸山の路線できたのかなと思います。小林秀雄は、文壇的な世界では相変わらず神様でしたが、大学の教育システムの中では、必ずしも評価されていなかった。
しかし、もしかすると、今の大学入試を作成する助教授クラスの若手が「それではいかん」と気づいて、国語の第1問に小林秀雄の文章をもってきたとすれば、これは希望の兆しだと私は思ったんですね。
永山則夫の精神鑑定からわかったこと
安西:私も、小林秀雄の著作は、『モオツァルト』などいろいろ読みました。『様々なる意匠』も。私自身は小林秀雄、それから小林秀雄に傾倒した江藤淳の書いているものに非常に引かれました。山折先生が言われたように、徐々にそういう時代のあり方を、大学人が察知し始めたというのは、そのとおりかもしれないと思います。

安西祐一郎(あんざい・ゆういちろう)
日本学術振興会理事長
1946年東京都生まれ。慶應義塾大学大学院工学研究科博士課程修了。カーネギーメロン大学人文社会科学部客員助教授、北海道大学文学部助教授を経て、慶應義塾大学理工学部教授。2001~09年慶應義塾長。2011年より現職。専攻は認知科学、情報科学。
今、大学入試が公で議論されるようになっていますが、たとえば九州大学は以前から、答えのない問題や文理融合の問題を入試に出しています。今、日本の大学生は1学年で60万〜70万人いますが、主体性というか、自分で生きるということをもう少し考えて、実践してほしいと思っています。
山折:3.11の大震災以降、防災、減災が非常に大きな課題になりましたよね。大学でも各専門家の間でも、協力し合った動きが出てきています。
ところが、同時に私が「あれ?」と思ったのは、自然災害のほかに犯罪が非常に凶悪化している事実です。毎日のように殺人事件が起こっています。社会学者は、統計的には殺人事件は減っていると言いますが、体感認識としては増えているという感じが依然としてあります。とすれば、その犯罪防止、犯罪を減らすための大学機関における共同研究や、研究課題の新たな設定といった動きが、もう少し出てもいいのではないかと思いますが、そうした動きはあまりありませんね。
安西:そうですね。犯罪の問題を扱うということはありますが、具体的にその殺人がどうして起こるのか、特に最近の社会の状況の中でどうして起こるのか、またそれをどうやったら解決できるのか。それについての横断的な研究は少ないと思いますね。
山折:私がこうした研究に興味を持ったきっかけは、戦後の連続4人殺人事件として世間を震撼させた永山則夫の事件(1968年から69年にかけて起きた連続ピストル射殺事件。永山は1997年の死刑執行まで、小説家として獄中で執筆活動を行った)と関連しています。当時、精神鑑定を担当した石川義博氏が、犯人と100時間にわたり対面調査を行い、精神鑑定書を書きましたが、最終的に裁判では採用されなかった。
その100時間にわたる対面調査は録音されていたのですが、これまで世間には知らされていませんでした。それを発掘してその全貌を明らかにしたのが、ノンフィクションライターの堀川惠子さんです。岩波書店から『永山則夫 封印された鑑定記録』が出ていますが、すごい作品です。
人間を支える「原風景」
山折:その作品を読んで、私は2つのことを知りました。

山折哲雄(やまおり・てつお)
こころを育む総合フォーラム座長
1931年、サンフランシスコ生まれ。岩手県花巻市で育つ。宗教学専攻。東北大学文学部印度哲学科卒業。駒沢大学助教授、東北大学助教授、国立歴史民俗博物館教授、国際日本文化研究センター教 授、同所長などを歴任。『こころの作法』『いま、こころを育むとは』など著書多数
ひとつは、彼が北海道の網走の生まれで、貧困と飢餓からものすごい虐待を受けていたこと。母親に3度捨てられたと言っているくらいです。そういう経験の中であの犯罪を犯したわけです。
一方、彼は知的にはかなりのものを持っていたようです。小説をずっと書き続けて、獄中で書いた『無知の涙』は、世間でも話題になりました。彼の告白の中に、自分は小学校のとき、石川啄木が大好きだったとあります。それからいろんな人生経験を経て、米軍基地からピストルを奪って第1の殺人を行う。その直前まで読んでいたのがドストエフスキーの『罪と罰』です。ラスコーリニコフが自己中心的な人間で高利貸しの老婆を殺す。その場面を読んだ直後に犯罪を犯しているんですね。
ところが彼は、その後にラスコーリニコフが娼婦のソーニャと出会って救われる話まで読んでいないわけです。これもやっぱりショックでしたね。あの悲劇の少年がその青春時代の同伴者にしたのが、啄木とドストエフスキーだったわけです。
そのことから、戦後の文学研究や文学教育のあり方について反省しました。私は犯罪防止という点から、文学の持っている力はものすごく大きいと思いますが、それを気づかせるのに、精神鑑定書が世に現れるまで20年が経っているわけです。
この問題は、司法ともかかわるでしょうし、文学者ともかかわるでしょうし、学校教育ともかかわります。それこそ、大学における文理融合の研究体制をどう築くべきかという問題にもつながります。
安西:人それぞれの教養といいましょうか、人が何かをするときの判断する土台というか、基準が何かということですね。永山則夫であれば、そういう人生の体験と生まれたときからの境遇というものがある。人それぞれいろんな体験がありますが、それを乗り越えて、判断するための土台を、どうやって身に付けたらいいのかということですね。
山折:そういうことになりますね。
安西:いわゆる殺人とか子殺しとか、その多くはやはり家庭環境が関与していると思います。それぞれ理由があるとは思いますが、そこを本当に乗り越えるだけの“よすが”というのが、本来の教養だと思っています。慶應の塾長をしていたときに「教養研究センター」を創設したのですが、そのとき思っていたのは、山折先生がおっしゃっているような、文とか理とかを超えた、人間の最も人間的な部分を、大学人自身がどう自省していくか、それを考える拠点を、学生への教養教育を考える以前に立てるべきではないか、ということでした。
山折:ちなみに、永山則夫の場合に印象的なのは、たくさん兄弟がいることです。いちばん上のお姉さんはちょっと知的に遅れているのですが、そのお姉さんと小さい頃、網走の海岸に行って砂遊びをした。そうした原風景が時々出てくるんですね。人間はそれぞれ子供の頃の忘れがたい、自然と触れ合う原風景みたいなものが心の奥にある。そして危機的な状況に再会すると、そういう原風景がよみがえってきて、それに支えられて乗り越えられると。
安西:話は永山則夫氏のほうが深刻だと思いますが、外国に出る若い人たちのほうがむしろ、日本の文化や歴史を考える機会が多いような気がします。
では、そのときの彼らの思いは、愛国心かというと、そのいわゆる国家という意味での日本を愛するのとはまた違う。それから、愛郷心というか、自分の具体的な故郷を思う心ともまた違う。原風景と先生がおっしゃるのはぴったりだと思いますけど、私はなんとなく大地というか、その日本の土を踏みしめて、何かを突き抜けたいちばん底にある帰るところといいましょうか。そういうふうなものを感じる。自分はそういう深刻な経験ではありませんが、外国で暮らしていてそう思いました。
山折:「それこそがまさに教養だ」ということですね。
安西:そうですね。
山折:それをわれわれは見つめてこなかった。
安西:そうですね。「終末期を迎えた日本の大学」というのは、そういう話を抜きにして、外から与えられた知識をただ教壇から流す教育をしてきたということだと思うんですね。
ゆで卵型の日本人、バナナ型の日本人
山折:内村鑑三がアメリカに行って、『余は如何にして基督教徒となりし乎』を書いていますが、最後のところで、アメリカの実質的な社会を徹底的に批判したあと、日本の森、川、自然の風景がいかに大事か、懐かしいかを書いています。愛国心、愛郷心というよりも、もう少し広がりのある、人間の生き方の根源を示すような話です。
安西:そうですね。私が外国にいたときに、そこで成功していた日本人の先輩は、アメリカが大好きで、そこで骨をうずめると常々言っていたのに、亡くなる直前になって「自分の灰は日本に撒いてもらいたい」と言われた。それはとても印象的でした。単なるノスタルジアというのでもなくて、何かがありますよね。
山折:先生はアメリカに何年くらい?
安西:3年です。
山折:かなり長いですね。北米の日系人の間で、こういうジョークみたいな話があります。だいたい日系のアメリカ人というのは2種類いる。1種類は卵型の、ゆで卵型の日本人。もう1種類はバナナ型の日本人。お聞きになったことあります?
安西:いえ、聞いたことないです。
山折:ゆで卵型というのは、外は白、中は真っ黄色、つまりは日本人。バナナ型というのは逆ですよ。皮は真っ黄色、そして中は白。この2種類あると。
安西:なるほど、面白いですね。
山折:今のアメリカに留学する日本の若者たちも、2~3年ではそういうことにはならないかな。
日本の3つの流れ
安西:たとえば留学という意味では、夏目漱石がロンドンに留学をして、非常に苦しんだと言われていますよね。明治になって日本は、それまでの儒教的な伝統などを背負いながら、近代と本当にぶつかったという気がするんですよね。単にただ知識をシャワーのように浴びて苦悩したというよりも、やはりいちばん奥の底の底で苦しんだというふうに読みとれます。
今の日本には3つの流れがあるように思います。ひとつは、長らく続く、明治近代以前の伝統的な日本。たとえば江戸時代の影響は、薄まっていますけれども、今でもある程度はあります。2つ目は、明治以降の外からの輸入的な近代の流れ。さらに3つ目として、インターネットなどの影響によるグローバル化の流れがあります。この3つの軸が混在しているわけです。
極端に言えば、漱石の時代の教養は「伝統」と「近代」の2つでした。それに対し、これからの若い人たちは、「伝統」と「近代」と「グローバル化」の3つの軸の中で、教養を考えなければなりません。それが、今までの時代とこれからの時代の違いです。だからこそ、これからの若い人たちには、先ほどから話に出ている「原風景」を、自分で自分の中に作り出していく機会を持ってほしいと思います。
つまり、欧米列強に追いつくのが日本の目標という時代ではなくなっている。そうした中で、世界の中での日本という感覚を持つ一方で、日本人としての伝統というか、「結局、帰るところは日本の大地だ」という感覚とは何かについて、しっかり考えるべき時がきている気がします。
(司会・構成:佐々木紀彦、撮影:今井康一)
※ 続きは次週掲載します